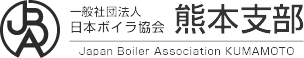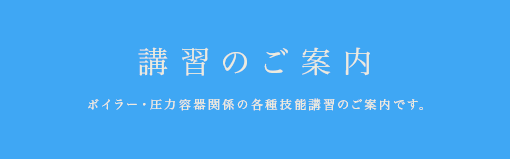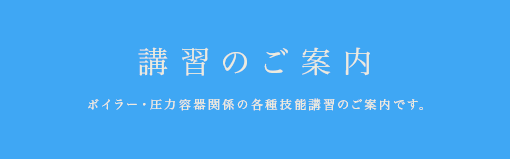
ボイラー実技講習(熊本労働局登録第5-5号)
- 内容
- この講習は、二級ボイラー技士免許を取得するための交付要件講習です。二級ボイラー技士免許は一定のボイラー修習か取扱経験又はこの実技講習を修了しなければ試験に合格しても免許は交付されません。この実技講習を先に受講して知識を習得してからの受験をお勧めします。またこの講習を受けていれば試験合格後いつでも(免許交付要件として生涯有効)すぐに免許の交付を受けることが出来ます。講習は3日間です。
講習会日程及び申込方法
ボイラー取扱技能講習(熊本労働局登録第5-4号)
- 内容
- この講習は、小規模ボイラーの取扱資格取得のための講習です。
講習は2日間です。
講習会日程及び申込方法
普通第一種圧力容器
取扱作業主任者技能講習(熊本労働局登録第5-3号)
- 内容
- この講習は、普通第一種圧力容器取扱作業主任者の資格取得のための講習です。
講習は2日間です。
講習会日程及び申込方法
化学設備関係第一種圧力容器
取扱作業主任者技能講習(熊本労働局登録第5-2 号)
- 内容
- この講習は、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者の資格取得のための講習です。
なお、化学設備(配管を除く。)の取扱いの作業に5年以上従事した経験を有することが受講資格となります。
講習は3日間です。
講習会日程及び申込方法
ボイラー取扱業務従事者
安全衛生教育
- 内容
- この講習は、ボイラー取扱業務従事者を対象とした安全衛生教育です。
事業者は、労働安全衛生法第60条の2第2項の規定に基づき、ボイラー取扱業務に現についている者に対して、概ね5年ごとに教育を実施するよう求めらています。これに伴い、事業者に代わって実施するものです。
講習は1日間です。
講習会日程及び申込方法
普通第一種圧力容器取扱
作業主任者能力向上教育
- 内容
- この講習は、普通第一種圧力容器取扱作業主任者を対象とした能力向上教育です。
事業者は、労働安全衛生法第19条の2第2項の規定に基づき、普通第一種圧力容器取扱作業主任者に対して、概ね5年ごとに教育を実施するよう求めらています。これに伴い、事業者に代わって実施するものです。
講習は1日間です。
講習会日程及び申込方法
化学設備関係第一種圧力容器
取扱作業主任者能力向上教育
- 内容
- この講習は、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者を対象とした能力向上教育です。
事業者は、労働安全衛生法第19条の2第2項の規定に基づき、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者に対して、概ね5年ごとに教育を実施するよう求めらています。これに伴い、事業者に代わって実施するものです。
講習は1日間です。
講習会日程及び申込方法
二級ボイラー技士免許試験
受験準備講習
- 内容
- この講習は、二級ボイラー技士免許試験の合格をめざすための受験対策の講習です。
対象:ボイラー取扱技能講習を修了した方で、小規模ボイラー取扱の経験のある方、ボイラー実技講習を受講し予備知識を得ている方、独学で受験勉強をされている方
公表問題を使用し傾向の分析及び重点的な解説を行う受験対策の一助とするものです。
但し、試験合格を保証するものではありません。講習は2日間です。
講習会日程及び申込方法
工作物石綿事前
調査者講習
- 内容
- この講習は、工作物石綿事前調査者の資格取得のための講習です。
講習内容は、当協会本部の会場からライブ配信します。
建築物、工作物、船舶の解体又は改修工事については、規模や請負金額に関わらず、工事対象となるすべての部材等に石綿が含まれていないか工事の前に調査を行う義務があります。(さらに、一定の規模・請負金額の工事にあっては、労働基準監督署への報告が必要となります。)
これまでは建築物等について、建築物石綿含有建材調査者の講習を修了し試験に合格した者にその調査を行わせることが義務付けられていますが、以下の特定工作物等については、2026年1月1日から「工作物石綿事前調査者」の講習修了者にその調査を行わせることが必要となります。
事前調査結果等の報告対象(特定工作物等)
・炉設備(反応槽、加熱炉、ボイラー・圧力容器、焼却設備)
・電気設備(発電設備、配電設備、変動設備、送電設備)
・配管及び貯蔵設備
一般社団法人日本ボイラ協会は、工作物石綿事前調査者講習の講習機関として東京労働局に登録(登録番号:石13-19)し、工作物石綿事前調査者を養成する講習を実施します。
本講習は、協会本部(東京)の会場で開催されている講習のスライドと講師の音声を、熊本の講習会場にライブ配信し開催いたします。講義終了後は、協会本部の講師とリアルタイムで質疑応答ができます。
講習は3日間です。(3日目は修了考査)
講習会日程及び申込方法
工作物石綿事前
調査者講習
修了考査再受験
- 内容
-
一般社団法人日本ボイラ協会熊本支部が開催した「工作物石綿事前調査者講習」を受講し、修了考査に不合格であった方は、講義を受講した年度の末日から起算して2年を経過するまでの間に、2回限り再受験することができます。
修了考査再受験は1時間40分です。
講習会日程及び申込方法
建築物石綿含有建材
調査者講習(一般)
修了考査再受験
- 内容
-
一般社団法人日本ボイラ協会熊本支部が開催した「建築物石綿含有建材調査者講習(一般)」を受講し、修了考査に不合格であった方は、講義を受講した年度の末日から起算して2年を経過するまでの間に、2回限り再受験することができます。
修了考査再受験は1時間40分です。
講習会日程及び申込方法